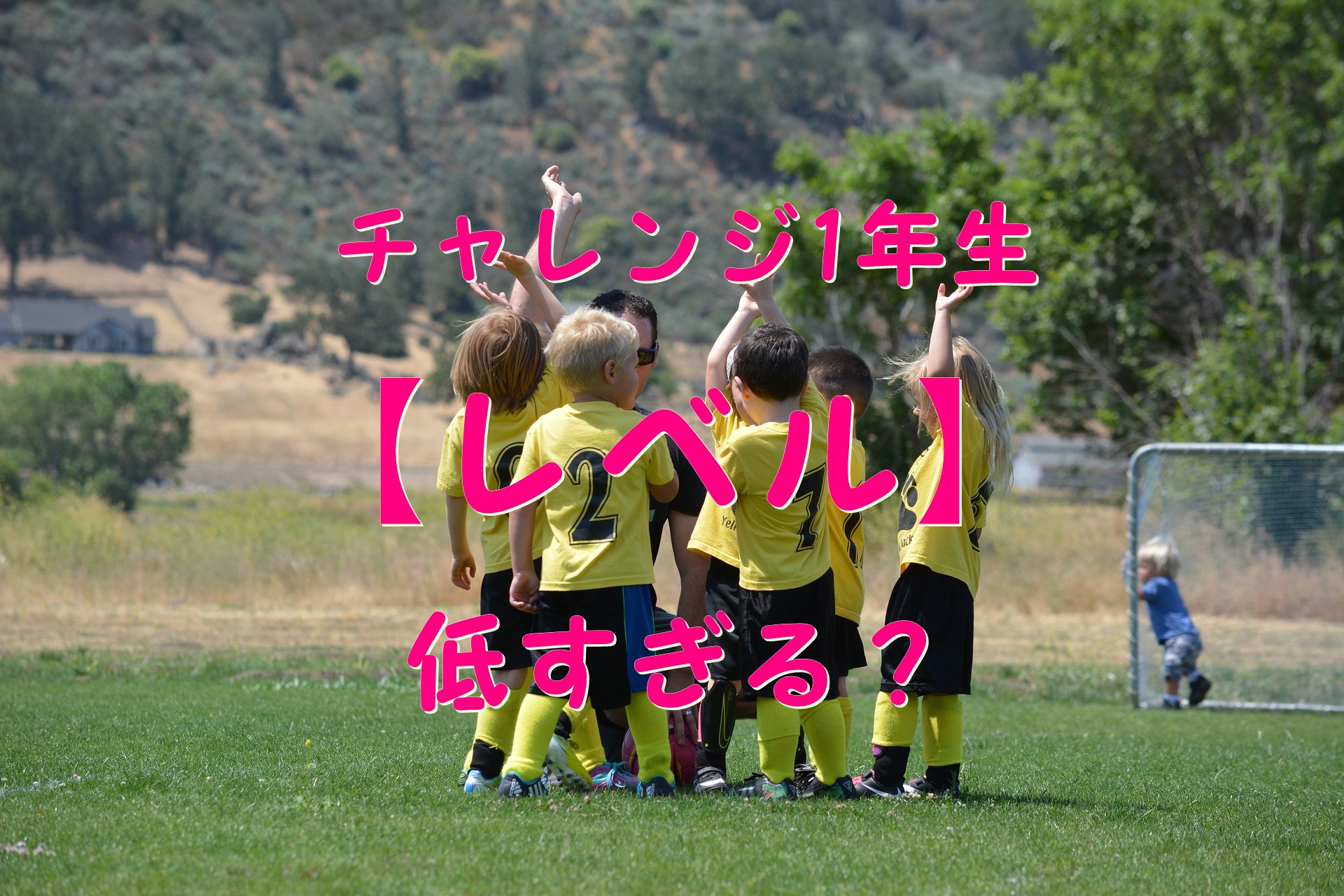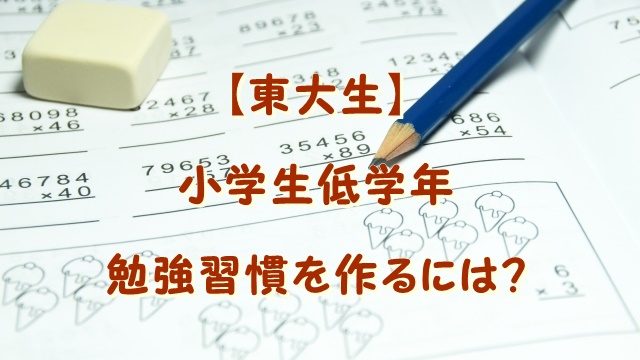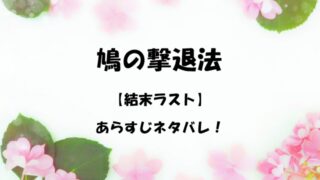中学受験では本格的に受験に取り組むタイミングが人によって違うこともあり、何年生から始めるのかで勉強の仕方も変わってきます。
そんな中で、Z会の中学受験コースは、3年生から受講が可能です。
そこで今回は、Z会の中学受験コースを小学校4年生から始める場合の勉強の仕方などをまとめてみました。
Z会の中学受験コースは4年生からでも大丈夫?
Z会では、小学生コースのハイレベルの講座もありますが、受験を考えるとなると中学受験コースへの切り替えが必要になります。
しかし途中からの受講となると、学校で習っていない単元も出てきますよね。
すると、勉強量が増えて子どもの負担も大きくなるのではないかと不安になります。
しかしZ会では、小学校4年生から中学受験コースに切り替える方も少なくありません。
そのため、サポート体制もしっかりしており。受験への切り替えが遅れてしまっても心配ないのです。
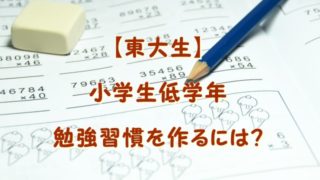
Z会の中学受験コースの遅れを取り戻す方法は?
小学校4年生から中学受験コースへ切り替えることで気になることといえば、遅れを取り戻せられるのか?ということですね。
得意・苦手分野があると不安も倍増してしまいます。
Z会では途中から中学受験コースを受講する方のために、科目ごとのアドバイスも紹介されているので、不安を解消しながら勉強に励めるようになっているのです。
そこで次に、各科目ごとに遅れを取り戻す方法を簡単にご紹介します。
国語
「国語」は、3・4年生から読解ポイントを学ぶため、途中から受講すると文章の読解が難しく感じられます。
しかし、練習問題をこなしていくことで少しずつレベルアップできるよう構成されているんです。
そして、5年生からは量をこなすことではなく、取り組んだ問題の解答・解説をしっかりと理解していけるような勉強法が勧められています。
算数
「算数」では、学校で学んでいる単元とZ会の中学受験コースで出題されている単元を埋めるための学習が最重要です。
Z会では、4年生の最終月までに、小学校6年生までの教科書範囲を一部の単元を除いたほとんどを学習し終える構成になっています。
そのため途中から受講した方には「追い付き教材」が用意されているのです。
そのため、学習プランやスケジュール管理をしっかりしながら、補助教材などを活用して学習を進めていくことで、遅れを取り戻す勉強法となっています。
《Z会の先取り学習スケジュール》
・3年生:整数の四則演算・単位換算と簡単な平面図形
・4年生:小数・分数の四則演算と平面図形・速さや割合、立体などを除いた小学6年生までの教科書範囲
・5年生以降:残りの範囲と中学受験特有の問題
・6年生:応用問題や発展問題へ
特に「Z会の入試算数の基礎30」という、30問をとにかく解くことが、Z会でも勧められています。
これは、完全に解かなくても、読むだけでもOK。
ただし、やはり問題数が少ないのは否めないので、その他の問題集もおすすめです。
また、まだ学校で勉強していない分野については、親が教えてあげられるといいのですが、親も忙しいので全学年対応のアプリを使って勉強するという方法もあります。
私がおすすめのアプリはスタディサプリです。
有料ですが、リーズナブルな料金でとても人気なんですよ^^
講師も、実際に中学受験塾の経営者などの方もいたりと、信頼できる講師が揃っています。
14日間無料で体験することもできるので、試してみるだけでもOKです。
無料で使いたい!っという方には「楽しい小学校 算数」というアプリがあります。
小学1年から5年生に対応していて、
理科
「理科」は4年生の間に、小学校6年生までの教科書範囲を先取り学習します。
しかし、複雑な内容は盛り込まれていないので、4年生から中学受験コースを受講する上で特別な準備をする必要ありません。
特に、5年生から基礎を発展していくカリキュラムが組み込まれていくので、Z会の4年生で学ぶ内容と学校での履修単元を見直し、しっかりと基礎を身につけていけるよう勉強をしていきます。
ただし、量も多くなってしまうので市販の問題集もいいと思います。
社会
「社会」は、4年生から地理→歴史→公民と入試に必要な基礎知識を身につける構成となっています。
そのため途中から受講する場合は、中学受験用の参考書などを使い、途中から受講した段階で学んでいない単元を自身で補う学習が必要です。
途中から始めた人の口コミです。
z会の中学受験コース4年生の勉強時間は?
小学校4年生から中学受験コースを受講し始めると、各科目それぞれに学校で学んだ単元より先に進んで勉強しなければいけないことも多いです。
そのため、これまで以上に勉強をする時間が増え、本人の負担が大きくなるのではと不安を感じることもあります。
Z会の中学受験コースで小学校4年生が4教科受講する場合、1ヶ月のうちZ会に取り組む日数を25日間としたとき、1日あたりの勉強時間は約60分(映像授業の視聴時間は含まない)と記載されています。
しかし、勉強の遅れを取り戻したり、苦手な単元を理解する時間も必要になってくるので、実際には記載時間の倍の勉強時間が必要になると思っておいたほうがいいです。
ドリルや添削問題にはそれぞれ時間の目安が書かれているので、子どもが自ら取りかかるものにプラスして、親のサポートが何より重要です。
Z会のみで受験に取り組む場合、学校で勉強していないものを教材のみでひとりで学習していくという体制が基本となります。
子どもの課題への理解度を確かめながら、学習プランを計画すると、理想としては小学校4年生の段階で週5日、1日1~2時間の自宅学習が習慣になれば心強いですね!
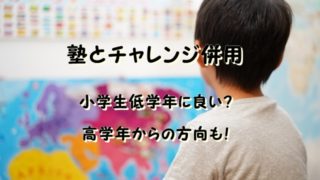
さいごに
今回はZ会の中学受験コースを、小学校4年生から始めるときの遅れを取り戻すための勉強法などについてみてきました。
学校の学習と受験に挑むための差を埋めるために、時間管理と計画が大切です。
上手くサポートして、子供が順調に進んでいけるようにしたいですね(^^)